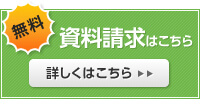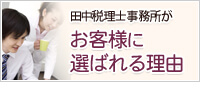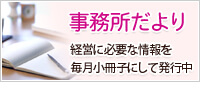�D�y �ŗ��m �D�y�s ��v����������Аݗ�/���������T�|�[�g
�N�Ǝ��̋�s�Z���A�������B�͎D�y����̓c���ŗ��m�������ɂ����k������
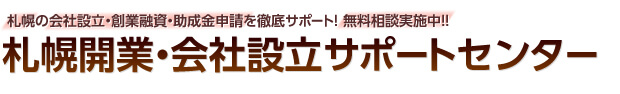

���g�b�v�� ��Аݗ��� �������� �������B�� �����\�� ��\�ҏЉ��� �X�^�b�t�u���O�� �������ē��� �A�N�Z�X�}�b�v��

>�D�y �ŗ��m/��v������ �c���ŗ��m�E�ИJ�m�������@ >�m��\��
�ߘa6�N���̊m��\���́A�ߘa7�N2��17���i���j�`3��17��(��)�̊��Ԃōs���K�v������܂��B
�܂��A�\���Ɠ����ɐŋ��̔[�t(�[��)��3��17��(��)�܂łɍs��Ȃ�������܂���B ���a�����������̐U�֔[�t����]�����ꍇ�ɂ́A�ߘa7�N4��23��(��)�ɐU�֔[���Ƃ���A�����A�\���Ɣ[�ł��x��Ă��܂����ꍇ�ɂ́A���ؐł��������Ă��܂��\���������̂ŁA�����ɒx��Ȃ��悤�ɂ��܂��傤�B
| �����敪 | ��� | �����i�Ŕ��j | ||
| ���Ə��� | ���F | PC���� | ���S | 66,000�~�` |
| �������K�v | 80,000�~�` | |||
| �ۓ��� | 92,000�~�` | |||
| �F�i������L�j | PC���� | ���S | 78,000�~�` | |
| �������K�v | 108,000�~�` | |||
| �ۓ��� | 120,000�~�` | |||
| �s���Y���� | ���F | PC���� | ���S | 58,000�~�` |
| �������K�v | 66,000�~�` | |||
| �ۓ��� | 72,000�~�` | |||
| �F�i������L�j | PC���� | ���S | 68,000�~�` | |
| �������K�v | 78,000�~�` | |||
| �ۓ��� | 88,000�~�` | |||
����Ő\��������ꍇ�ɂ͕ʓr�����ɂȂ�܂��B�ȈՉې�20,000�~�`�A��ʉې�26,000�~�`
�Ȃ��A����Łi�n������Ŋ܂ށj�̖@��[�������ߘa7�N3��31���i���j�ŁA�U�֔[�ł́A�ߘa7�N4��30���i���j�ł��B
| �����敪 | ��� | �����i�Ŕ��j |
| ���n�����i�y�n.�����j�����p�Ȃǂ͗v���k | 1����ɂ��� | 28,000�~�` |
| �Z��ؓ��������ʍT�� | 20,000�~�` |
| ��Ô�T�� | �Œ�6,000�~�`�ҕt�z��10% |
| ��t���T�� | �Œ�6,000�~�`�ҕt�z��10% |
�p�O�P�D�ǂ�Ȑl���m��\��������K�v������̂ł����H
- (�P)�l���Ƃ��c��ł����
-
�@�l�łȂ��Ă��A�l�Ŏ��Ƃ��s���Ă�����͊m��\�������Ȃ�������܂���B
�l���Ǝ�̕��̊m��\�����@�ɂ́A��F�\����Ƣ���F�\�����2�p�^�[��������A�ǂ���̐\�����@�ł����܂��܂��A��F�\�����I������ƁA���ō�55���~�܂ŐF�\�����ʍT�����邱�Ƃ��ł���ق��A�Ԏ���3�N�ԌJ�z�T�����ł���Ȃǂ̃����b�g������܂��B
�������A��F�\���������ꍇ�ɂ́A�������L��ł̋L���Ƣ�F�\�����F�\������̓͂��o���K�v�ƂȂ�܂��B
��e-tax�ɂ��d�q�\��������ƁA�F�\�����ʍT���z��10���~���� 65���~�ƂȂ�܂��B - (�Q)�s���Y�����̂����
- �y�n�⌚���Ȃǂ̑ݕt�ɂ��s���Y�����̂�����͊m��\�����K�v�ł��B
- (�R)���̔N���Ɏx�����鋋�^���̎������z��2,000���~�����
- (�S)�m��\��������Ƃ����ȕ�
-
�E�}�C�z�[�����w���܂��̓��t�H�[����������
�E��Ô��N��10���~�ȏ�x��������
�@�i��O�F���v���������z����200���~�����̏ꍇ�́A����5���ȏ゠����j
�E����29�N�����Z���t���f�B�P�[�V�������V��
�@ �����ʗp���i�̍w���12,000�~�ȏ゠���
�E��t��������
�E�ȑO�̉�Ђ�r���ސE���N�����������Ă��Ȃ���
�p�O�Q�D����8�N�O���ʋƂ��c��ł���A�n�Ǝ����F�\�������Ă��܂����A�ߘa6�N���̐\���ŋC�����邱�Ƃ�����܂����H
- �@��L�p�O�P�D�̂Ƃ���u�F�\�����ʍT���z�v���ߘa2�N�����55���~�Ɉ����������܂������A e-tax�ɂ��d�q�\���܂��͓d�q����ۑ����s���ƁA�F�\�����ʍT����65���~���܂��B
- �A�z��҂��]�҂Ƃ��Ďg�p���Ă���ꍇ�A�z��҂͋��^�����҂ƂȂ�܂����A���Ɛ�]�ҋ��^�ƕ}�{�e���T�����Ƃ����Ԃ��Ď��܂���B
�p�O�R�D���́A���N�i�ߘa6�N�j�y�n�p���܂����B
���p���6,000���~�A�y�n��20�N�O�ɕ���葊���������̂ŁA���̎擾���z�͕s���ł��B����Ǝ҂ɒ���Ƃ���200���~�x�����܂����B
���̑��̎����͂���܂��A�ӂ邳�Ɣ[�łȂNJ�t������Ă��܂���B
�ߘa2�N�����b�T���z���Ⴄ�悤�ɂȂ��������ł����A���������̐ŋ��i���ŋy�ђn���Łj�͂�����ʂł����B�i�}�{�T������ی����Ȃǂ͂Ȃ��Ƃ��Čv�Z���ĉ������B�j
���n�����́A�y�n�̔��p�������A���̎擾��Ɣ��p���ɂ�����������Ȃǂ̔�p���������������z�ɂȂ�܂��B���Ȃ��̂悤�ɁA�y�n�̎擾��킩��Ȃ��ꍇ�ɂ́A���������z��5�������z���擾��Ƃ��邱�Ƃ��ł��܂��B
�ŗ��͔��p�̔N��1��1���ɂ����ď��L���Ԃ�5�N����ꍇ�A�����œ�(�������ʏ����Ŋ܂�)15.315���A�y�яZ���ł�5���ł��B
�Ŋz�v�Z�ɍۂ��ẮA�������z������b�T���z�����������܂��B��b�T���z�́A�ߘa���N���܂ł͏������z�ɂ�����炸�ꗥ38���~�ł������A�ߘa2�N������͏������z�ɉ����āA�����ł͍ō�48���~�A�Z���ł͍ō�43���~�ƂȂ�܂����B�������z��2,500���~����Ɗ�b�T���z�͂���܂���B
���������āA���Ȃ��̏ꍇ�A�Ŋz�̌v�Z�͎��̂悤�ɂȂ�܂��B
���n�����F6,000���~�i�y�n�̔��p����j�|�o300���~�i�擾��j+200���~�i����j�p��5,500���~
�����Ŋz�F5,500���~�~15.315����842���~(��)�ߘa1�N�̂悤�Ɋ�b�T���z�����������Ƃ͂ł��܂���B
�Z���Ŋz�F5,500���~�~ �@ 5�� �@��275���~�@
�@���v�@�F�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@ 1,117���~
�p�O�S�D���͔N��i�ߘa6.12.31 ���݁j68�ł��B�N���������ߘa6�N����250���~�ł��B���̍ȁi�N��62�j�����l�ɔN��������70���~�ł��B�ߘa���N�Ɣ�r���A�ύX�_���������狳���Ă��������B
- (�P)�ߘa2�N�����A�N�����������Ȃ��҂ɂ��ẮA���I�N�����T���z��10���~�����������A���̑����b�T���z���ꗥ10���~�����グ���܂����B����āA�ߘa���N�Ɣ�r���A�ېł���鏊�����z�ȂǂɕύX�͂���܂���B
�i���v����2,400���~���鍂�����҂ɂ����ẮA���v�����z�ɉ����Ċ�b�T���z���������A���v������2,500���~����ƁA��b�T���z���Ȃ��Ȃ�܂��B�j - (�Q)�N�������̑��ɁA���^����������l���A���̍��v�������z��10���~����ꍇ�A���������z���v�Z����ۂɉ��L�̋��z�����^�����̋��z����T�����܂��B
�i10���~���x�j�@�@�@�i10���~���x�j
�p�O�T�D�����ł͂ǂ̂悤�ȕ��@�Ŕ[�t����̂ł����H
- (�P)���Z�@�ւ̗a���������ł̐U�֔[��
- �U�֔[�ł�����]�̏ꍇ�A�[�Ŋ����܂łɂ��炩���ߌ����U�ւ̈˗������o����K�v������܂��B�˗����͉��L�y�[�W���_�E�����[�h���邱�Ƃ��ł��܂��B
���m�葱��] �\�������ŋy�ѕ������ʏ����ŁA����ŋy�ђn������Łi�l���Ǝҁj�̐U�֔[�Ŏ葱�ɂ��[�t - (�Q)�����ł̔[�t
- �����ɔ[�t����Y���āA���Z�@�ւ܂��͐Ŗ����ɂĔ[�t���邱�Ƃ��ł��܂��B
- (�R)�C���^�[�l�b�g���𗘗p���ēd�q�[�ł�����@
- ���O�ɓd�q�[�ł̎葱�����K�v�ƂȂ�܂��B
- (�S)�R���r�j�G���X�X�g�A�Ŕ[�t
-
���Œ��z�[���y�[�W�łp�q�R�[�h�쐬�E������A�R���r�j�G���X�X�g�A�Ŕ[�t�B
�i�[�t�z��30���~�ȉ��̏ꍇ�j - (�T)�N���W�b�g�J�[�h�[�t
-
���ŃN���W�b�g�J�[�h���x���T�C�g���^�c����[�t�ϑ��҂Ɉϑ�������@�B
���Ȃ��A�[�t�Ŋz�ɉ����Č��ώ萔����������܂��B
�p�O�U�D�ߘa6�N9��1���Ɍl���Ƃ�p�~���A�@�l����i�g�D�ύX�j���܂����B
�ߘa6�N�̊m��\���͂ǂ̂悤�ɂȂ�܂����B
�@�l����ɍۂ��A�@�l���l���甃����������Y������ꍇ�́A�l�̎��Ə����܂��͏��n�����ȂǂƂȂ�܂��̂ŁA������Y�ꂸ�Ɍv�Z�����Ă��������B �܂��A�ߘa6�N���Ɍl���Ƃ�p�~���Ă��܂��̂ŁA�ߘa6�N���̎��Ə������v�Z����ۂ́A�ߘa7�N�x�i�ߘa6�N���̏����Ɋ�Â����́j���l���Ɛł̌��ϊz��K�v�o���ɂ��邱�Ƃ��ł��܂��B
�p�O�V�D�T�����[�}���ł����A�]�ɂ𗘗p�����킸���ȕ�����������܂��B�m��\���͕K�v�ł����B
- (�P)���ߐ悪�P�����ŁA�����ŔN������������Ă�����́A���̑����u�������z�v�̍��v�z��20���~�ȉ��̏ꍇ�́A�m��\������K�v�͂���܂���B
�������A������Ђ̖��������̓�����Ђ�����ƒ������ȂǗ�O�ƂȂ�܂��B - (�Q)�N���������������ߐ�ȊO��������^���Ă�����́A�N������������Ȃ��������^�́u�����v���z�ƁA���̑��́u�����v�����v�z��20���~�ȉ��̏ꍇ�́A�m��\������K�v�͂���܂���B
���̏ꍇ�A���^�����̎������z����A�����T���i�G���T���A��Ô�T���A��t���T���A��b�T���������j�̍��v�z�������������c��̋��z��150���~�ȉ��ŁA����ɂ��̑��̏������z��20���~�ȉ��̏ꍇ�́A�\���s�v�ƂȂ�܂��B
��L�ɂ��Ă͂܂�Ȃ��ꍇ�́A�m��\�����K�v�ƂȂ�܂��B
�p�O�W�D�N�����������Ă��܂��B�m��\���͕K�v�ł����B
�������A�N�����猹������Ă���Ŋz�������āA��Ô�T����Љ�ی����T���Ȃǂ�����ꍇ�́A�m��\��������Ɛŋ����߂�ꍇ������܂��B
�܂��A�����Łi���Łj�̊m��\���͕s�v�ł����A�Z���Łi�n���Łj�̐\�����K�v�ȏꍇ������܂��̂ŁA�����ӂ��������B
�p�O�X�D�T�����[�}���Őŋ��̊ҕt�������̂ł����A�Ŗ����֍s�����Ԃ��Ȃ��Ae-tax�ɕK�v�ȋ@�����������̂���Ԃ�������܂��̂ŁA�X���Ŋm��\�����邱�Ƃ͂ł��܂����B
���t�ɂ���o����ꍇ�ɂ́A�K���X�֖��͐M���ւ𗘗p���Ă�������(�䂤�p�b�N�A�䂤���[���A�䂤�p�P�b�g�A�N���b�N�|�X�g�͕s�i���^�[�p�b�N�͉�))�B
�ߘa7�N1���ȍ~�͎����������Ȃ��Ȃ�܂����̂ŁA�ߘa6�N���̊m��\�����e-tax�Ő\�����������悢�ł��傤�B
�p�P�O�D�ߘa6�N���ɁA���ȏ��L�̎����2,000���~�Ŕ���A�V�����Ƃ��w�����ďZ�ݑւ��܂����B���̎��n�E�X���[�J�[�̕�����u3,000���~�܂ł͏����ł�������Ȃ����x������v�ƕ����܂������A���̏ꍇ�m��\������K�v������̂ł��傤���B
�܂��m��\���̎��ǂ̂悤�ȏ��ނ��K�v�ł����B
�}�C�z�[��(���Z�p���Y)�����Ƃ��́A���n��������ō�3,000���~�܂ōT�����ł�����Ⴊ����܂��B(���Z�p���Y�����n�����ꍇ��3,000���~�̓��ʍT���̓����Ƃ����܂�) ���̓�����邽�߂ɂ́A�m��\�������邱�Ƃ��K�v�ł��B�܂��A�m��\�����Ɏ��̏��ނ�Y���Ē�o���Ă��������B
- (�P)���n�����̓���(�m��\�����t�\���v�Z����)[�y�n�E�����p]
- (�Q)����̔����_��������̑O���ɂ����āA�Z���[�ɋL�ڂ���Ă����Z���Ə��n�����Z��p���Y�̏��ݒn���قȂ�ꍇ�́A�ːЂ̕��[�̎ʂ��ȂǁB
- (�R)�}�C�i���o�[�J�[�h�̎ʂ�
�p�P�P�D�ߘa6�N4��1���Ȍ�A�}�C�z�[�����Z�ݑւ����ꍇ�ɁA���ӂ��ׂ����Ƃ�����Ƃ̂��Ƃł����A�ǂ�Ȃ��Ƃł����H
�ߘa2�N4���Ȍ�̃}�C�z�[���̏��n����́A�V���ɋ��Z�����N�̑O2�N�ƌ�3�N�ԁi����1�N�j�́A���v6�N�Ԃ́A3,000���~�̓��ʍT�������ꍇ�ɂ́A���̐V���ɂ��Ă̏Z��[���T���͎��܂���B
�p�P�Q�D���́A�T�����[�}���ŋ��^����������Ă��܂��A��Ô�̎x�������O�N�ߘa5�N�ɓ��@��������20���~������܂��B
������ł��m��\������A�ŋ����߂��Ă��܂���?
�ŋ���߂��Ă��炤�\�����ҕt�\���Ƃ����܂����A�����ҕt�\���͈�Ô���x�������N�̗��N1��1������5�N���s�����Ƃ��ł��܂��B
�]���āA�ߘa5�N�̈�Ô�̊ҕt�\���ɂ��ẮA�ߘa6�N1��1������ߘa10�N12��31���܂Ŋҕt�\�����邱�Ƃ��ł��܂��B
�p�P�R�D�ߘa6�N12���ɐf�@������Ô���N���W�b�g�J�[�h�����ɂ��A�ߘa7�N1���Ɉ������ɂȂ�܂����B
���̈�Ô���ߘa6�N�̈�Ô�Ɋ܂߂邱�Ƃ��ł��܂����B
����ėߘa7�N1���ɃJ�[�h��Ђ������������Ă��A�N���ɕa�@�̑����ŃJ�[�h���ς��Ă���A�ߘa6�N���̈�Ô�T���ƂȂ�܂��B
�p�P�S�D�Ƒ��S���̈�Ô�����i�b�j���S���x�����܂����̂ŁA���̑S�z���܂Ƃ߂Ď��̈�Ô�T���̑Ώۂɂł��܂����H
�w�[�ŎҖ{�l���́A�[�Ŏ҂Ɛ��v����ɂ���z��҂₻�̑��̐e���̂��߂Ɉ�Ô���x�������ꍇ�x
�ƂȂ��Ă���A���̐��v����ɂ���Ƒ��̏����ɐ����͂���܂���̂ŁA�b�����ۂɂ��̈�Ô�S���Ă���̂ł���A�b���m��\���ň�Ô�T�����邱�Ƃ��ł��܂��B
�p�P�T�DiDeCo�i�l�^�m�苒�o�N���j�Ɏ��̍Ȃ��������Ă��܂��B���̊|�������i�v�j���x�����Ă��܂��B���̏ꍇ���̏����T���ɂł��܂����H
�p�P�U�D�m��\�����Ȃ������ꍇ�͂ǂ��Ȃ�̂ł����H
����A�[�߂�ׂ��ŋ�������̂ɁA�\�������܂łɊm��\�����Ȃ������ꍇ�A���ؐł△�\�����Z�Łu�[�߂�ׂ��ŋ���15%�i�[�߂�ׂ��ŋ���50���~�����镔����20%�j�v���{���̐ŋ��i�����Łj�̑��ɉۂ����܂��B
����̓}�C�i���o�[�ɂ��A�l�̏������Ǘ�����邽�߁A���\���ɑ��������͌������Ȃ��Ă���Ǝv���܂��B
�p�P�V�D�ӂ邳�Ɣ[�ł͊m��\�����Ȃ��Ă��悢���Ė{���ł����H
�u�ӂ邳�Ɣ[�Łv�͎葱�����ȑf�����A����27�N����͈��̏����������ƂŊm��\�������Ȃ��Ă��ŋ��̍T��������d�g�݂ƂȂ��Ă��܂��B
���̏����Ƃ͉��L��7�ɂȂ�܂��B�����S�Ė������l�͊m��\�����s�v�ł��B
- (�P)��Ј��ŁA���ɔN���������s���Ă���l
- (�Q)�N��2000���~�ȉ��̐l
- (�R)���^��1�̉�Ђ��������Ă���l
- (�S)�m��\�������Ȃ��l
(���z�ʉ݂̐\���Ȃǂ�����K�v�̂Ȃ��l���Ô�T��������K�v�̂Ȃ��l�Ȃ�) - (�T)�u����27�N4��1���Ȍ�v�̊ł��邱��
- (�U)1�N�Ԃ̊悪5�����̈ȉ��ł���l
- (�V)���Ŋz�T���ɌW��u�\������\�����v�����������̂֒�o�����l
�p�P�W�D�ӂ邳�Ɣ[�Łi��t���j�Ɍ��x�z������ƕ������̂ł����H
�y�n�Ȃǂ̏��n�������Ȃ��ꍇ�ŏZ��[���T�����Ȃ��ꍇ
�Z���ł̉ېŏ������z �~ 2�� ���ߌW��
+2,000�~�Z���ł̉ېŏ������z��195���~�ȉ��̏ꍇ�@0.84895
�Z���ł̉ېŏ������z��195���~��330���~�ȉ��̏ꍇ�@0.7979
�p�P�X�D�ӂ邳�Ɣ[�ł����ԗ�i�����炢�܂������A����ɑ��ŋ��͂�����܂����H
�������A���ɖ����ی����̏����Ȃǂ�����ꍇ�A����ƍ����Čv�Z���邱�ƂɂȂ�̂ŁA�ېł���邱�Ƃ�����܂��B
�p�Q�O�D����n�������c�́A���v�@�l���ɑ����t�������ꍇ�A�@���̔N�̂����̓����t���̍��v�z�ƇA���������z����40�������z�Ƃ̂����ꂩ���Ȃ����z����2,000�~�����������u��t���T���̋��z�v���A���̔N���̏������獷�������Ƃ��ł��܂��B���̏ꍇ�́u���������z���v�Ƃ͂ǂ̂悤�ȋ��z�ł����B
�]���܂��āA�}�C�z�[���p�����ꍇ�ɂ́A��t���T���̌��x�z������Ă��܂��B
�p�Q�P�D�ߘa6�N���ɁA����҂ɂ₳�����o���A�t���[���C�H�������܂����B
�ǂ̂悤�ȍH�����ŋ��̍T���ΏۂƂȂ�̂ł��傤���H
- �@���ȏ��L�ŁA�����Ȃ̋��Z�̗p�ɋ��p���Ă���Ɖ��ɁA���L�̂悤�ȁu����ғ����Z���C�H���v�����A���̔�p�̊z��50���~����ꍇ�ł��B�������A�⏕�������Ă���ꍇ�ɂ́A���̋��z���T��������̔���ƂȂ�܂��B
- �A�Z��[���𗘗p���Ă��Ȃ��Ă����ʐŊz�T�����邱�Ƃ��ł��܂��B
- �B�������A���̃o���A�t���[���C�H���ɂ��ă��[����L���Ă���ꍇ�ɂ́A�u�Z��ؓ��������ʍT���v�Əd�����Ď邱�Ƃ͂ł��܂���B
- �E�Ԉ֎q�ł̈ړ���e�Ղɂ��邽�߁A�ʘH�܂��͏o�������g������H��
- �E���z�̂����K�i��P�����A�K�i��V�����ݒu�E���ǂ����z���ɂ₩�ɂ���H��
- �E����
- (�P)�����s�ׂ����������Ղ����邽�߁A�����̏��ʐς��L������H��
- (�Q)�����̂܂�����Ⴍ����H��
- (�R)�Œ莮�̈ړ���E���ݑ䂻�̑��A����ғ��̗����̏o��������Ղ�����H��
- (�S)����ғ��̐g�̂�₷�����邽�߂̐�������ݒu����H��
- �E�g�C��
- (�P)�r���s�ׂ₻�̉�����Ղ����邽�߁A�g�C���̏��ʐς��L������H��
- (�Q)�a���g�C����m���g�C���ɂ���H��
- (�R)�m���g�C���̍�������������H��
- �E�肷������t����H��
- �E���̒i������������H��
- �E���O�ɖʂ���o��������яオ�肩�܂��A�����̏o�����̒i��������������H��
- �E�g�C���E�����E�E�ߏ��E���̑��̋����E���ցE���������Ԍo�H�̏��ނ��A����ɂ������̂Ɏ�ւ���H���Ȃ�
- �C50�Έȏ�̐l�ŁA�v����v�x���̔F����Ă���ꍇ
�p�Q�Q�D��Ј��Ŋ��ɉ�ЂŔN���������Ă��܂��B�����J����t���}�A�v���Ŏ�ŏW�߂Ă������i��܂������A�m��\�����K�v�ł����B
���̔��p�������̂��u�����p���Y�v�ł��邩�ǂ����A�܂��u�c���ړI�v�ɊY�����邩�ǂ������傫�ȃ|�C���g�ɂȂ�܂��B
��{�I�ɁA���������Ă����m���Ȃǂ̐����p���Y���������Ă���ꍇ�́A�����p���Y�̏��n�ɂ�鏊���i���n�����j�ƂȂ�A�N��20���~���鏊���ł��m��\���͕s�v�Ƃ���Ă��܂��B
�����p���Y�Ƃ́A�ʏ�̐����̏�ŕK�v�ȁu�Ƌ�E�Y��E���E�ߕ��v�Ȃǂ̂��Ƃ������܂��B
�܂�A�e���r��e�[�u���E�֎q�A�Ɠd�AT�V���c��X�J�[�g�Ȃǂ̈ߕ����A�������邤���Ŏg�����̂̂��Ƃł��B
�������A�M�����E��E����E�����i�ȂǂŁA1����1�g�̉��z��30���~������̂��A���p���ē��������͉ېőΏۂƂȂ�܂��B
�uCD�E�Q�[���E�{�v�Ȃǎ�ŏW�߂��R���N�V�����i���A���̉��l�������A����E�����Ƃ���1����1�g��30���~����l�����̂�����̂��A���p�����Ƃ��͊Y�����邱�ƂƂȂ蒍�ӂ��K�v�ł��傤�B
���y�n�E�����ȊO�̏��n�̏ꍇ��
�@���n�v�����������z�|�i�擾��{���n��p�j
�A���n�����̋��z�����n�v�|���ʍT���z
���ʍT���z�͔N��50���~�����x�Ƃ��A���n�v��50���~�ȉ��ł���ꍇ�ɂ́A���̏��n�v�����ʍT���z�ƂȂ�܂��B
�p�Q�R�D��(�b)�́A����21�N5����1,000���~�Ŏ擾�����y�n���D�y�s�ɂ���܂����B
���̓y�n��ߘa6�N8���ɁA�s���Y�Ǝ҂�ʂ��āA1,800���~�Ŕ��p���܂����B�����ނ˂ǂ̈ʂ̐ŋ���[�ł��Ȃ�������Ȃ��̂ł��傤���H
�Ȃ��A���̓T�����[�}���ŁA���^�����ɂ��Ă͊��ɔN���������I�����Ă��܂��B
�l�̕����A����21�N���Ɏ擾���������ɂ���y�n����27�N�ȍ~�ɔ��p�����ꍇ�A�܂��͕���22�N���Ɏ擾�����y�n����28�N�ȍ~�ɔ��p�����ꍇ�ɂ́A���L�̂悤�ȓ��Ⴊ����܂��B
- �@���̓y�n���̏��n�����̋��z�o���p���z�|�i�擾��{���n��p�j�p��1,000���~�ɖ����Ȃ��ꍇ�ɂ́A���̏��n������0�i�[���j�ƂȂ�܂��B
�b�́i1,800���~�|1,000���~��800���~�j��1,000���~�ł�����A���n�����̋��z�́u�Ȃ��v�ƂȂ�܂��B - �A�������A���̓�����邽�߂ɂ́A�m��\��������K�v������܂��B
- �B�܂��A�e�q��v�w�ȂǓ��ʂȊԕ�����擾�����y�n���́A���̓���̑Ώۂ��珜����܂��B
�p�Q�S�D�m��\���ɂ���Ĕ[�t���ׂ������ł��A�v���Ă�����葽�����z�ł����B
3��15���܂łɑS�z�����̂�����ꍇ�A�����������ł��܂����H
���@�Ƃ��ẮA�m��\�����̑��\��
- �@3/15�i�U�֔[�ł̏ꍇ�A4��23�����[�t�ƂȂ�܂��B�j�܂łɔ[�߂�1��ڂ̋��z�ƁA
- �A5/31�܂łɔ[�߂�2��ڂ̋��z���A2�敪����
1��ڂ̋��z�ŕS�~�P�ʂ̒[�����x�����悤�ɁA�[�t���ׂ��Ŋz�̑S�z��2����1�ȏ���w�肵�܂��B
�������A���[����z�ɑ����q�ł�������܂��B
���q�ł̊����́A�ߘa6�N1��1���ȍ~�̊��Ԃ��A�N0.9���ł��B
�v�Z���ꂽ���q�ł̊z��1,000�~�����̏ꍇ��̂Ăł��̂ŁA���[������z���A��53���~�����ł���Η��q�ł��������܂���B
�p�Q�T�D�l�b�g�V���b�v�Ń|�C���g���t�^�������T�𗘗p���Ĕ����������܂������A���̐\�����Ȃ��Ă悢�̂ł��傤���H
��ʓI�ɂ́A�|�C���g���p�����́A�ꎞ�����Ƃ��ċ敪������A�N�Ԃ̃|�C���g���p�ɂ�錻������������50���~�̈ꎞ�����̓��ʍT���z�͈̔͂ł���ΐ\���s�v�ł��B
�����A�|�C���g�̐��i�ɂ���ẮA�G�����ɂȂ���̂�����܂��̂ł����ӂ��������B
�p�Q�U�D���Q�҂����Ô�A�Ԏӗ��y�ё��Q�������Ȃǂ�������Ƃ��́A�����ɂȂ�܂����H
��ʎ��̂Ȃǂ̂��߂ɁA��Q�҂����Ô�A�Ԏӗ��A���Q�������Ȃǂ�������Ƃ��́A�����̑��Q���������͔�ېłƂȂ�܂��B
�������A���Q�������̂����ɁA���̔�Q�҂̏����̋��z�̌v�Z��K�v�o��ɎZ���������z���Ă邽�߂̋��z���܂܂�Ă���ꍇ�ɂ́A���̕�Ăꂽ���z�ɑ������镔���ɂ��ẮA�������z�Ƃ���܂��B
�Ⴆ��
(�P)���i�̔z�����̎��̂Ŏg�����̂ɂȂ�Ȃ��Ȃ������i�ɂ��đ��Q�������Ȃǂ�������ꍇ
(�Q)�ԗ����X�܂ɔ�э���ő��Q�����ꍇ�ŁA���̓X�܂̏C�����Ԓ��ɉ��X�܂������Ƃ���
�@�@���ؗ��̕�C�Ƃ��đ��Q�������Ȃǂ�������ꍇ
��L�̑��Q�������Ȃǂ́A�K�v�o��ɎZ���������z���Ă邽�߂̂��̂ł���A��ېłƂ͂Ȃ炸�A���Ə����̎������z�ƂȂ�܂��B
�p�Q�V�D��N���@���āA��Õی�������������̂ł��������ɂȂ�܂����H
�����ی�����x��������@���t�����p���t���Ȃǂ̋��t���́A���z�Ɋւ�炸��ېłł��B
����ېłɂȂ鋋�t������
�@�E���@���t��
�@�E��p���t��
�@�E�ʉ@���t��
�@�E���a�i�ЊQ�j�×{���t��
�@�E��Q�ی����i���t���j
�@�E���葹�����t��
�@�E����f�f���t��
�@�E���莾�a�i�O�厾�a�j�ی���
�@�E��i����t��
�@�E���x��Q�ی����i���t���j
�@�E���r���O�E�j�[�Y����ی���
�@�E���ی����i�ꎞ���E�N���j�@�Ȃ�
�p�Q�W�D���͑�H�Ƃ��Čl���Ǝ�ł����A������̗v��������ߘa6�N10��1�����C���{�C�X�̓o�^��\��������ł̔[�ŋ`���҂ƂȂ�܂����B
�ߘa4�N���܂ł͖��N���㍂��1,000���~�Ȃ������̂ŁA����ł̐\�����������Ƃ�����܂���B�u2������v�Ƃ������Ƃ��悭���ɂ��܂����ǂ��������Ƃł����H
�l���Ǝ�̏ꍇ�A�ߘa5�N�`�ߘa8�N���ɂ��ẮA�O�X�N�i����ԂƂ����܂��j�̉ېŔ��㍂��1,000���~�ȉ��ł���Ȃ�A���㍂�i�Ŕ����z�j�ɌW�����ł܂�u����Ŋz�v��2����[�ł���悢�̂ł��B
�p�Q�X�D���N�A�����̔����ŗ��v���ł܂����B�m��\�����K�v�ł��傤���H
�u��������v�́u��������v��I�����Ă���ꍇ�́A�����A�m��\���͕K�v����܂���B
�������A���̊����ɂ��Ĕz�����Ă���A��������Ă���ꍇ�A�m��\������Ɛŋ����߂邱�Ƃ�����܂��B�������A�z��ҍT����}�{�T���̑Ώێ҂͊m��\�����邱�Ƃɂ��A���̍T���ΏۂƂȂ�Ȃ��Ȃ�ꍇ������܂��̂Œ��ӂ��ĉ������B
�p�R�O�D��N�A�����̔��p�i���n�j�ő������o�Ă��܂��܂����B
���n���i�����̔��p�m���n�n�ɂ�鑹���j���o���ꍇ�A3�N�Ԃ́u�J�z�T���v�����邱�Ƃ��ł��܂��B
�u�J�z�T���v������ɂ͊m��\��������K�v������܂��B��������𗘗p���Ă���ꍇ�ɂ́A�،���ЂȂǂ��瑗���Ă��Ă���u�N�Ԏ�����v�̋��z��p���Ċm��\�������܂��B
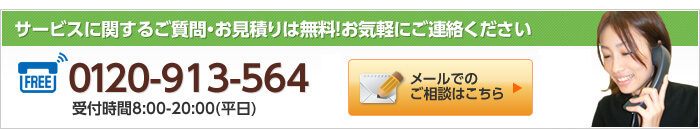
�� ���l����@ �� �l���ی���j